Post Passion Fruitsのメンバーである小林毅大も参加していた「上演のタネをまく」を見た感想を書きます。本上演イベントはPARA主催の演劇コース参加者によるもので、ルールは『3人以上の人が集まり、十五分の「上演」を作る。』というものでした。7月20日に行われたこのイベントでは、途中休憩や席移動などを挟みながら、15分×9つの上演が行われました。イベント直後には、演劇コースの主任講師の一人である川口智子とゲストの額田大志による、30分程度の講評(アフタートーク)もありました。実際に見ていない方には分かりづらい部分もあるかと思いますが、当日のパンフレット画像も掲載しておきますので、適宜参考にしてください。
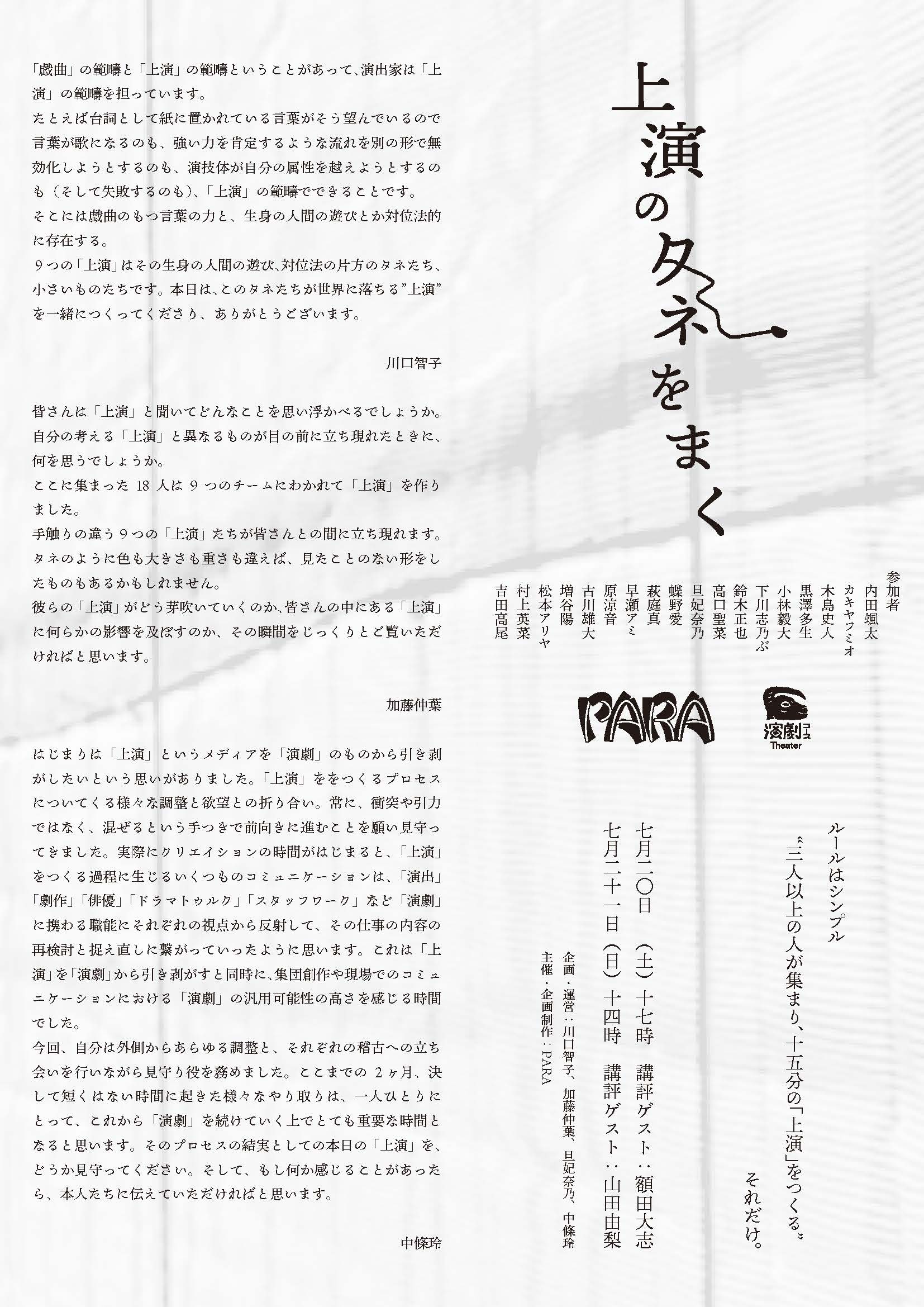
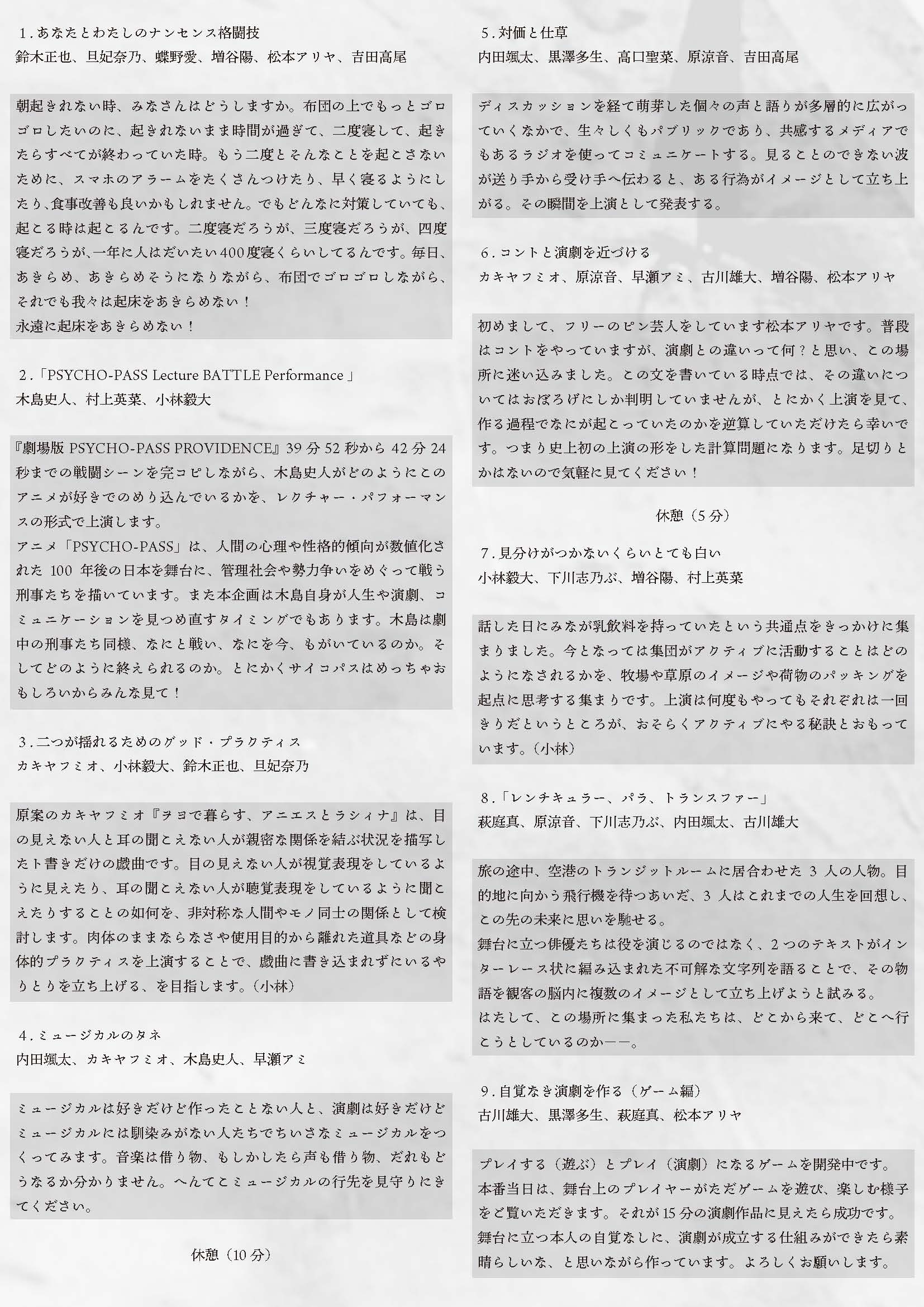
1.「あなたと私のナンセンス格闘技」
この上演は、TikTokやYouTubeショート、AIの動作などの短編混在性や同時並列性、時代象徴性などを想起させるものでした。上演内容の特徴的な部分を抜粋すると、情緒性(エモ)に訴えかける短尺で次々に切り替わるスマホDJ的音楽を背景に、過呼吸、野獣、シャトルラン、腹ばい運動、仏壇のお参りなどが実況中継され、寝起きにおける起床の苦しみを中心とした、身体性に対する断片的な内容のメモがその場でコピーされ、観客に配布されるというものです。
上演の結論が「スマホを手放すことができない」という現代社会のコモンセンスに集約される(ナンセンス → コモンセンス)のではなく、カオスな運動が林立したまま終わる(ユーモア過剰 → ナンセンス)、またはもう一段メタに踏み込んだナンセンス(アイロニー過剰 → ナンセンス)で終わると、よりテーマが深掘りできたのではないかと思います。
観客に対する起立の強制は、上演内容とは無関係かつ理不尽に起立させられたままの鑑賞体験を強いられる(ナンセンス)ともいえるし、上演における寝ることを禁止された起床運動と対比して鑑賞における座ることを禁止された起立運動を強いられる(ナンセンス)ともいえる。つまりこの構造は、あなたと私(観客と演者)の間で繰り広げられる「ナンセンス格闘技」であるとも解釈可能であり、それが独特な上演/鑑賞体験を生み出している点は面白いと思いました。
2.「PSYCHO-PASS Lecture BATTLE Performance」
この上演は、個別具体的な実存、状況、関係性に対する宛先はあるものの、誰に届くかは分からない手紙(誤配)のようなものでした。その数少ない宛先の対象者として私自身も含まれているため、完全に公平な評価とはいえないかもしれませんが、私の個人的なベストでした。
上演内容としては、アニメの戦闘シーン、ショートコント、レクチャーパフォーマンスなどの形式や文法を取り入れ、分かり合えなさを朗読と身体のパフォーマンスの分離によって表現していました。特に印象的だったのは、小林の語りで「絶縁関係」と「友人関係」が対比され、過去の自分の行いを肯定しつつ、友達であり続けることができたのではないかと懐古する場面でした。
この結論は、一人の個人が悩んだ末に出した一つの美しい結論です。しかし、私には別の見解もあります。以下は、これもまた個人的な宛先はあるものの、誰に届くかは分からない手紙として書きます。
私の見解としては、某宗教による疑似家族的連帯をアンカーとして、某人の「友達」というトリガーが作用していたのではないかと考えています。つまり「友達」というキーワードが、自他の境界を曖昧にする口実になっているように感じました。自分の手に負えない状態に陥り、他人に迷惑をかける状況になってまで「友達」を救済しようとする。このような状況が破綻した時に、一体何が起こるのか。そこまでの背景が十分に考慮された上に至った結論だったのかは気になりました。
浦沢直樹『20世紀少年』に登場する「ともだち」のように、「友人関係」もまた「絶縁関係」と同様に暴力的な関係性になる可能性があります。「それでも」友達であることは相手を肯定する手段となるかもしれませんが、某宗教における「離婚禁止」が「それでも」絶縁を許さないという暴力であるように、「それでも」友達であり続けることも一種の暴力と捉えられるかもしれません。
特定の個人がセカンドチャンスを与えることは美しい行為であるかもしれませんが、セカンドチャンスはむしろ社会全体が与えるべきものであると考えるならば、「絶縁」もまた相手を肯定する手段となり得ます。つまり、個人の関係性における「絶縁」は、単に相手を否定するための手段ではなく、社会がその人に新たな機会を与えるための手段にもなり得るのだと私は信じています。
3.「二つが揺れるためのグッド・プラクティス」
この上演は、良くも悪くも、演者と観客の体験が最も乖離しているものでした。言い換えれば、岸井大輔の「戯曲の観客は演者である」という言葉を最も体現していたように感じました。複雑な文脈が入り組んでいるものの、この上演のテーマを一言で表現するなら「共有不可能な身体性を持つ他者の代弁とコミュニケーションの可能性」といえるでしょう。
その具体例をテクストから抜粋すると「目の見えない人と耳の聞こえない人が親密な関係を結ぶ状況」を「ト書きだけの戯曲」から立ち上げる試みといえます。戯曲や代弁、コミュニケーションには常に誤読や誤解がつきまといます。手段が言語であれ、身体表現であれ、完全な理解は存在しません。村上春樹はかつて「理解というものは、つねに誤解の総体に過ぎない」と述べました。ところが現代においては、誤解が「暴力性」として捉えられ、エビデンスを伴わない、もしくは本人の気持ちに沿わない「理解」は糾弾されることが増えました。
そのような背景を踏まえれば、この上演の試みは、誤解や誤読の極限を探求し、その結果としてどのような理解が立ち上がるのかを実験する上演であったと読み替えても良さそうです。しかし、このような理解は上演後しばらくしてふと思い付いたものであり、上演中は眠気との孤独な闘いが繰り広げられていました。芸術表現において、退屈さをどう捉えるかは一つの大きなテーマです。退屈さが誤読や誤解の可能性を拡張するならば、そのような間延びした時間を通した理解を肯定することもできるかもしれません。
「あなたと私のナンセンス格闘技」とは、流れる時間性の観点において対極にあるような上演ですが、二つの構造に誤解と理解、演者と観客の対比が含まれることで、良いプラクティス(グッド・プラクティス)になっていました。
4.「ミュージカルのタネ」
この上演は、とりあえず笑えます。一見それ以外に語ることもないように思いますが、思うところを徒然なるままに書いてみます。演劇にミュージカルの文法を無理やり取り入れた内容で、演者が慣れないミュージカルの演技を矢継ぎ早に続けることで、癖になる笑いが生まれていました。
個人的にはミュージカルが昔から苦手で、理由としてはベタですが、突然脈絡なく歌い出す展開についていけないためです。お酒でいえば、ミュージカルはワインに似ていると感じます。恐らくワインの文法に沿ってその魅力が分かれば美味しいのでしょうが、そもそも酒が人体に有毒な以上、一旦不味く感じる方が正常ではないかと疑ってしまいます。結果として、すべてが嘘なのではないか、もしくは無理やり矯正した結果なのではないかというリアリティの方が強くなってしまいます。
つまり、私には前提が共有できず、そこから繰り広げられる世界に没入できないのです。もちろん様々な営みがある前提の元に行われるので、ミュージカルやワインだけを批判するのはおかしいのですが、日本人としては特にそう思ってしまいます。しかし、この上演では、そのような違和感がむしろ強調されることで、逆に気にならなくなる効果がありました。
一つ気になったのは、資本主義的な状況に対する苦しみが背景に見え隠れすることです。これは他の幾つかの上演にも共通するテーマであり、観客が共感しやすいテーマとして選ばれた可能性もありますが、意外と本質的なテーマでもあると感じました。
というのも、資本主義とは、すべてが代替可能であることを露呈する運動ともいえます。お金という一元化された基準の元で、すべてが代替可能になることが苦しみを生み出す一方で、利便性も生み出します。演技や音楽、仕事なども含めてすべてが代替可能であるならば、演劇もミュージカルに代替可能であり、ミュージカルも演劇に代替可能です。このような徹底した代替可能性を露呈し、笑ってみせること。その技術と可能性が、上演を通して示されていたように感じました。
5.「対価と仕草」
この上演は、演劇と美術(インスタレーション)の融合を目指しているように感じました。編み物をしながら朗読されるテクスト、複数のラジオを通して流れる暖かみのある音声、ゆっくりと往復移動する木製のキャスターパネル、そしてまたしても起立させられる観客。これらすべての要素が私を眠りへと誘いました。
上演の装置として、テクスト、編み物、マイク、ラジオ、キャスターパネルなど、複数のメディアが独立して存在していました。これはミクストメディア的な融合(複数のメディアが一つに統合される)を目指していたわけではなく、各メディアが独立性を保ちながら、場面ごとに複雑で多様な関係性を編むように構成されているように感じました。
インスタレーションでは、場として時間と空間の設計が重要です。落ち着いたラジオの語りにより複数の時間が流れ、キャスターパネルが移動することで空間の区切りが変化し、新たな形を見せ始めました。今回の試みは、このように異なるメディア同士を可変的な関係性の中で関連付けることで、プリズムの光のような多面性を持つ上演/インスタレーションの場を実験したものと捉えられます。
このような場において、人間というメディアが他のメディアとどう関係するかは重要な要素です。途中、他のイベント参加者がラジオの近くに移動して音声を聴いていたので、観客の移動も許容されていることに気付きました。しかし、移動を促すアナウンスがなかったため、その場で鑑賞を続けました。観客の導線や移動をどう設計するか、メディアとしてどう位置付けるかは、観客との相互関係において成立する上演としても、観客を空間に巻き込むインスタレーションとしても無視できない要素です。これらの点がもう少し明確に深堀りされると、さらに発展した形の上演が期待できると感じました。
6.「コントと演劇を近づける」
「コントと演劇の違いは何か」をテーマとしたこの上演は、一見すると深いテーマに見えますが、罠にハマる可能性が高いテーマ設定でもあります。芸術全般においては「既存の文脈における定義更新性」が定義の内部に含まれるが故に、定義自体が自己言及的に変化するという再帰的なメタ性が含まれます。「アートとは何か」や「演劇とは何か」という自己言及的なテーマが常に問われ続けるのはそのためです。
この背景に関連して「ジャンルAとジャンルBの違いは何か」というテーマもよく議論されますが、これらのテーマは他の状況や差異によってその関係性が決まるため、単独で定義することは難しい印象があります。例えば今回の上演が演劇の文脈で行われれば演劇と見なされ、お笑いライブの文脈で行われればコントと見なされるでしょう。つまり上演の内容自体よりも、観客や舞台を含めた環境の設定の方が大きな影響を持つように思えます。さらにこのようなジャンル定義論争は、実際には関係者以外にはあまり重要視されないことが多く、テーマ設定としては内向きに感じました。
このように内容より環境がジャンルを定義するという大前提を踏まえた上であえていえば、ユーモア(ネタ)の方向からナンセンスを追求するのがコントで、アイロニー(メタ)の方向からナンセンスを追求するのが演劇と捉えることはできるかもしれません。ネタとメタの最小公倍数として「寿司、お化け、総合病院」などの要素を召喚し、複数の異なる演算子による計算(演者による演技)を経てコント/演劇を出力する構造を、計算問題と位置付けることは可能でしょう。
「寿司、お化け、総合病院」はそれぞれ「海外文脈、ホラー文脈、領域横断文脈」に接続可能な要素を持っています。例えば「寿司」ではなく「Sushi」、「ハリウッド・ホラー」ではなく「ジャパニーズ・ホラー」、「異種格闘技」ではなく「総合格闘技」といった具合に。このようなネタとメタが絡み合う時代性を汲み取り、要素をバランスよく料理してみせるセンスには、お笑いの嗅覚を感じました。まとめると、この上演は異なる文脈のネタ=メタを素材として、どのような演算子による計算を行えばコント/演劇の同一性が出力されるのかという実験(計算問題)と捉えることができます。ただし、環境(観客、舞台、文脈)という変数が計算に甚大な影響を与えるため、これらを構造に含めた上での計算問題を改めて解いてみたいと思わされました。
7.「見分けがつかないくらいとても白い」
この上演は、日常性(即興性)、稽古(上演)、キャラクター性(実存)の観点から新たなアプローチを考えさせられるものでした。ここで三つの演劇理論を比較してみます。
平田オリザの「現代口語演劇」は、自然な演技を通じて日常性を再現することに重点を置いています。演者はノンプレイヤーキャラクターとして稽古を重ね、自然な演技を習得し、それを舞台で再現します。ここでは、演出として静かな演劇を目指し、即興性は排除されています。
岡田利規の「超口語演劇」は、より砕けた口語と過剰な身体性を強調します。演出によって、即興的に見える日常会話を基にしつつ、身体表現の過剰性により観客に言葉と身体のリアリティを与えます。ここでは、キャラクター的な過剰性が日常性に反転するという新たな演劇表現を模索しています。
本上演は、これらの演劇理論とは異なり、「極限口語演劇」ともいえるアプローチを取っています。日常性と即興性、稽古と上演、キャラクターと実存の区別をなくし、それらの中間項としての演出を極力排除しています。この結果、これらの要素の区別が限りなくゼロに近づき、見分けがつかない状態に達しています。これは、まるで数学における極限のように、要素間の距離が無限に小さくなることで一体化(収束)するような演劇と捉えることもできるでしょう。
例えば、上演中にたまたま雷鳴が轟いた瞬間がありました。演者たちはすぐに窓に駆け寄り、その状況について語り始めました。これは日常性と即興性が最も重なり合った場面であり、非常に印象に残りました。また、各演者が何かの稽古をしているかのように見え、上演前後や上演中に観客とラフに絡む様子も、稽古と上演の境界を曖昧にしていました。さらに、普段の小林を知っている観客からすると、彼の素の受け答えを上演中に見せられると少しギョッとしましたが、それもキャラクターと実存の区別がないように感じられました。つまり、この上演の意図は、各要素が最初から完全に区別なく上演されるのではなく、要素間の距離が限りなくゼロに近づき(見分けがつかないくらい)、それが偶然性による緩やかな共同性(乳飲料=とても白い)に繋がるかどうかを実験することにあったといえるでしょう。
終演後の交流会で小林にもらったチャイが普通に美味しかったことも印象的でした。通常、消え物は演者が消費するものですが、今回は上演空間で作られたチャイを観客にも提供することで、演者と観客の距離を接近させていました。同時にここでは、日本人とインド人の庶民感覚、カフェと舞台、日常空間と上演空間の距離がゼロに近づいているとも捉えられます。演出を排除しつつ、演劇の共同性を成立させる方法を探るという意味では、この上演が最も可能性を感じる「タネ」であったと思います。
8.「レンチキュラー、パラ、トランスファー」
この上演は、複数のテクストとダンス的身体の同期/非同期、つまり意味と非意味を往復する抽象言語同士の翻訳/誤訳可能性が交差する場所で生まれるコミュニケーションについての演劇と捉えました。具体的には、本の朗読、リゾートファッション、回想の物語、タコのように滑らかな動きなどが織り交ぜられ、言語と身体が交互に編まれていく様子が描かれていました。それはまるで新しいコミュニケーション方法が生まれる瞬間に立ち会っているかのような不思議な感覚でした。
これらの要素が交差する場所として、空港という舞台を選んだことは非常に理にかなっています。空港は出会いと別れ、未来と過去、夢と懐古の象徴として、文化芸術的に興味深い場所だからです。特にトランジットルームは、これらの象徴をさらに強調する場所として機能します。ここでレンチキュラー(両眼視差)、パラ(並列)、トランスファー(転移)のキーワードを踏まえると、前述した要素が並列的に交差する編み目を、視差的な立体的イメージ(共通言語)へと転移させるための通過点(トランジット)として捉えることも可能です。狙いとしては「対価と仕草」と近いものも感じますが、本上演は美術の要素を取り入れた複数メディアによるプリズム的多面性を追求するのではなく、あくまで演劇の要素内で演者=人間も装置に含めた、視差的立体性を目指すアプローチが強調されています。
また個人的に空港というキーワードで想起するのは、ブライアン・イーノの『Ambient 1: Music for Airports』です。このアルバムは、アンビエント・ミュージック(環境音楽)を世に知らしめるきっかけとなったもので、エリック・サティによる『家具の音楽』の「家具のように日常生活を妨げない音楽」というコンセプトを引き継ぎつつ、「空港の音楽」として私的空間から公共空間への発展を象徴しています。上演中、各演者は役としてというよりは、環境として存在しており、その異なる環境同士がコミュニケーションを試みているように感じました。まさしく、私的言語同士のぶつかり合いが公共言語として立ち上がる瞬間を待ち構えるかのように。
しかし、私の精神はこの時点で狂気的な限界に達しようとしていました。イベント中の度重なる起立強制、席移動、15分ごとに上演される異なる性質のパフォーマンス。これらが交感神経と副交感神経、覚醒状態と睡眠状態の切り替えを頻繁に要求し、精神の中に抑圧されていた何かが解放される状態に陥りました。この状況は、私に中学時代の記憶を呼び起こしました。
中学校の先生から伝え聞いた話ですが、高校受験の際、母校で突出して優秀だった先輩が、テスト中にストレスの限界に達し、大声で叫んで退場させられたというのです。その先輩は一度聞いただけで授業内容をすべて覚えるという特異な才能を持っていました。私はその先輩と面識もなく名前も知りませんし、私の高校受験に結果として何の影響も及ぼしませんでしたが、その逸話だけが現在まで意識的には忘れ去られたまま、潜在的には心に深く刻まれていました。そして、何故かその先輩が叫んだ状態が自分の精神に突如として乗り移り、上演中に既に叫んでしまったのではないかという妄想に毎秒取り憑かれ、必死にそれが現実ではないことを確認し続けることに精神のリソースを費やしました。
前述したようにこの憑依状態はおそらく、この上演自体の性質のみならず、イベント全体の性質に関連しています。しかし、あえて本上演と結びつけるとすれば、意味不明な妄想や幻想が他者から乗り移り、その意味が追体験的に分かるもしくは現実に出現してしまう可能性についての考察を深めることはできます。ホルヘ・ルイス・ボルヘス『トレーン、ウクバール、オルビス・テルティウス』で、幻想国家「ウクバール」がいつの間にか現実を侵食していたように。ダグラス・ホフスタッター『ゲーデル、エッシャー、バッハ』で、無意味から意味を獲得するシステムが出現するように。「レンチキュラー、パラ、トランスファー」で、そのような幻想的な無意味と現実的な意味が交差する瞬間の追体験をすることも、この上演の潜在的な機能の一部だったのではないかと思い込むのは、私の錯覚のなせる業なのでしょうか。
9.「自覚なき演劇を作る(ゲーム編)」
この上演は、「プレイする(遊ぶ)とプレイ(演劇)になるゲームは成立するか」をテーマにしたものでした。プレイという言葉に「遊び」と「演劇」の意味を重ねることは、岸井の影響を感じさせます。ただし岸井はプレイを「戯曲」と「おもちゃ」と「作品」に重ねているのに対し、本上演ではプレイを「演劇」に重ねており、それらの差異は少なからず存在します。仮に本上演のゲームのルールを「戯曲」とすると、ルールに沿って遊ぶ演者たちは存在しますが、そこには「演出」が存在しないともいえます。つまり、本上演の潜在的な試みを言い換えると「演出を介さずに戯曲(ゲームルール)と演技(演者)があれば演劇は成立するか」ということになりそうです。
私が最も気になった点は、演者のプレイ空間としての長方形のテーピングによる区切りと、その周囲を囲う観客の関係性についてです。もちろん大前提として、プレイ空間と鑑賞空間を区切ることで、演者と観客の安全性を確保する配慮があったはずです。しかし、私にはこの境界線が、立ち入り禁止の安全領域/闘争領域の境界線のようにも見えました。つまり、これは中世のコロッセオのように現代の闘技場を戯画化したもなのではないかと思ったのです。
どういうことかを、具体的な上演内容を交えて説明します。男性演者4人によるゲームは、鬼ごっこやだるまさんが転んだなどの幼少期の定番ゲームなどを土台とし、肉体的なぶつかり合いや椅子の上に乗って走り回るなどの競争性や危険性を含むものでした。つまり境界線の内側で行われる遊びは、象徴化されたホモソーシャル的なじゃれ合いの連鎖ゲームのようにも見え、境界線はその治外法権のための免罪符として引かれたように感じました。であるならば、このプレイ空間は、罪を問われない安全領域でもあり、同時に競争するための闘争領域でもあるという二面性を持っています。
なぜこのような予防線が必要かといえば、ホモソーシャルなゲームは現代のポリティカル・コレクトネスの観点から無邪気に楽しむことが難しくなったからでしょう。イヴ・セジウィック『男同士の絆:イギリス文学とホモソーシャルな欲望』によれば、ホモソーシャルとはミソジニーとホモフォビアに基づく男性間の緊密な関係性を指します。つまりホモソーシャルは単純に有害な男性性についての概念ではなく、ある種の排他性を共通了解とした共犯関係にある誰しもに関係のある社会的な概念だということです。
ここで本当に重要なのは観客の存在です。なぜなら、この上演は、闘技場で演者により戯画的にプレイされるホモソーシャルのゲームを笑いながら鑑賞する観客も含めた共犯関係の告発として捉えることも可能からです。アフタートークで額田が「このゲームに参加したいたいとは思わなかった。この上演を笑って鑑賞することはできなかったが、観客がこんなに笑うんだと思って意外だった」という趣旨の話をしていました。もちろん私の述べたような文脈や意味での発言ではないですし、明言もしていませんでしたが、潜在的にはこのような論点も内在しているように感じました。ホモソーシャルのゲームは演者だけでは成立せず、観客の存在があって初めて成立する以上、自覚なき演劇の俎上ではある意味同罪なのだということです。
本上演については、テーマ設定の仕方なども含めて「コントと演劇を近づける」に似た感想を持ちましたが、ゲームのルール設定と繋ぎの流れなどにおいて、明らかに演劇的な要素が組み合わされていたように感じられました。これはプレイして演劇になるゲームを作るという意図によるものでしょうが、むしろゲームをプレイしたら演劇に見えるという現象について考えてみるのも面白い気がします。例えば、演者の4人が家庭用ゲーム機で遊ぶ様子を、ゲーム実況含めて15分間垂れ流してみる。この場合、遊びから演劇的な要素を徹底的に排除することで、ゲームのプレイがどのように演劇として機能するのかを、ラディカルに検証することができます。実況中継というテーマは、今回のいくつかの上演に共通する特徴でもあり、ゲーム実況は現代のゲームと演者/観客の関係性を考察する上で重要な論点です。ただし、今回の読み解きの内容に従えば、実況中継により自覚を促す作用は、確かに少し笑えないのかもしれません。
さて、今までは9個の上演について一つ一つ語ってきましたが、最後に全体についての感想をまとめてみます。あえて細部の差異を切り落とし、今回の上演を一言でまとめるならば「演劇から演出という役割、もしくは演出家という職能を排除しても上演は成立しうるか」という問いに対して、その「タネ」となりうる9つの営みを実験的に提示した上演であったといえそうです。
もちろんそのようなテーマ設定はどこにも記述されておらず、主任講師の川口が演出家であることを考えると意図的なものではあり得ないでしょうし、実際には演出もあったのかもしれません。しかしここで私が言いたいのは、実際にその意図やテクストの提示があったかどうかではなく、結果として内容的/構造的にこのように捉えられる演劇が並び、それは参加者たちの無意識から自然発生したものであると感じたということです。アフタートークの中での「演出や演出家というものの避けられ具合、人気のなさに驚いた」という趣旨の川口の発言も、その一つの裏付けになるでしょう。
では、演出/演出家の役割とは一体何でしょうか。スタイルは多様ですが、その重要な役割の一つとして、戯曲と上演、演者と観客を繋ぐための内部批評、つまり敵対性の役割は避けられないものです。そして、この内部批評≒敵対性が暴力性として忌避されている。つまり、演劇という営みから従来の演出という役割、もしくは演出家という職能が排除されつつある流れがあるのだと感じました。ちなみに演出/演出家の話とは直接関係はありませんが、パンフレット表面の企画・運営陣を除いて、裏面の各上演におけるテクストの文責を負っていたのが小林だけだったという事実にも、この流れに漂う雰囲気が反映されているように思います。なぜなら暴力性と責任は批判を含めて引き受ける/回避するという意味において、不可分に連動する概念でもあるからです。
アフタートークでは「内容としてバトル(対戦)ものが多い傾向にあったが、何故なのか」という問題提起がありました。その原因の分析は特に深堀りされませんでしたが、個人的にはこれは演出/演出家が排除されつつある流れと表裏一体の現象かと思いました。つまり、内部批評≒敵対性が暴力性の象徴の一つとして表面上では避けられるが故に、人間の潜在的な欲望や対立の提示の発露として、演劇そのものの中にバトル(対戦)が立ち現れてくるのだと考えられます。
またこの流れに対して、元PARA代表であり演劇コースの元主任講師であった岸井についても言及せざるを得ません。
PARA神保町 体制変更について(ご報告)
PARA神保町辞任のご報告とご挨拶
上記のPARA名義の報告と岸井大輔名義の報告では、そもそも前者がコンプライアンス上の問題と岸井個人に対する代表としての資質の疑義を踏まえた上での体制変更の話をしているのに対し、後者はそれらの問題について一切触れず、組織におけるコレクティヴの自律運営論(リーダーシップ論)を踏まえた上での体制変更の話になっており、そもそも話が前提からして嚙み合っていません。その原因の一旦は、事の発端となった事件における当事者のプライバシー保護、名誉侵害の恐れにあることは理解できますが、PARAの関係者や演劇コース参加者に対してさらなる混乱を招いたことは想像に難くありません。またこのような対応が良かったかどうかはさておき、この件を経て、演劇コースの主任講師は岸井から川口を含む3人の女性講師に変更になった経緯があります。
今回の上演全体は改めて振り返ってみても、岸井の影響が非常に大きいと感じました。影響としては個別に言及した箇所の他にも、岸井の演劇の基本的なスタイルは「他ジャンルで遂行された形式化が演劇でも可能か」というものであり、他のジャンルから形式や文法を借りてくるという点で、今回の上演全体にも共通する特徴が見られます。さらに演出/演出家が排除されるという特徴についても、岸井は劇作家として、戯曲自体を作品と見なし、戯曲を演出した上演を作品と見なさない立場を取っていました。この点の影響も、今回の上演において無関係ではないでしょう。これらの岸井の演劇の特徴を踏襲しつつ、演劇界におけるハラスメント対策としての演出/演出家の排除の流れや、岸井がPARAの運営から退いたことなどを含め、今回の上演はこれらの混沌とした状況に対する参加者たちの潜在的な信念と抵抗が混ざり合った疑問と実践の「タネ」でもあったのかもしれません。
岡田斗司夫は「ホワイト社会」という言葉を使い、コロナ禍を経て2030年から2040年にかけて到来するであろう、表面的な正しさや綺麗さ、共感性などが称揚される社会を予言しています。この清潔で漂白された社会では、内面や本質、事実がどうであれ、表面的な「いいひと」しか評価されないという特徴があります。このホワイト社会による漂泊の傾向は、一般社会にもパラダイムシフト的な革命を起こすということですが、芸術文化の領域では既にポリティカル・コレクトネスやキャンセルカルチャーの文脈で激論が交わされている状況でもあります。
しかし、このホワイト社会の到来が進行する中で、二つの懸念点があります。まず、ホワイト社会によってキャンセルされた主体が半地下化し、カルト化の傾向を強める可能性があること。次に、内部批評を行わないという暴力性の忌避や内輪的テーマの流行が、結果としてそのような表現を有料で見せられる観客への暴力に転換される可能性があることです。詳細は本筋とは異なるためここでは避けますが、これらの点は今後ますます顕在化してくる問題でしょう。表層的には歴史修正主義的に固有名が消されてホワイト化し、深層的には行き場を失った固有名によるカルト化が進行する。演出家やキュレーターによる内部批評、批評家による外部批評も、等しく「イヤなひと」の暴力的な営みとして淘汰され消滅していく。
表面的な加害性が地球上から退場させられる一方で、人類は存在するだけで等しく有害であるという現実は残り続けます。我々が本当に向き合うべきは、前者のホワイト社会的で表面的な暴力性ではなく、後者の本質的で避けられない暴力性であり、それらをどのように引き受け直すかです。最後にまとめ直すと、今回の上演はホワイト社会的な上演の「タネ」であると捉えることもできます。しかし私が本当に見たいのは、深層的な暴力性や有害性と向き合ったタネであり、そのタネから咲く花にこそ、上演の未来や本当の可能性があるのではないでしょうか。